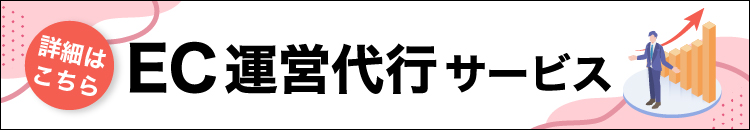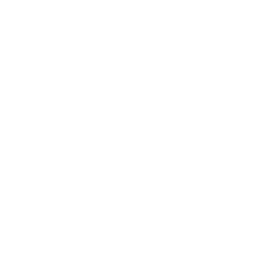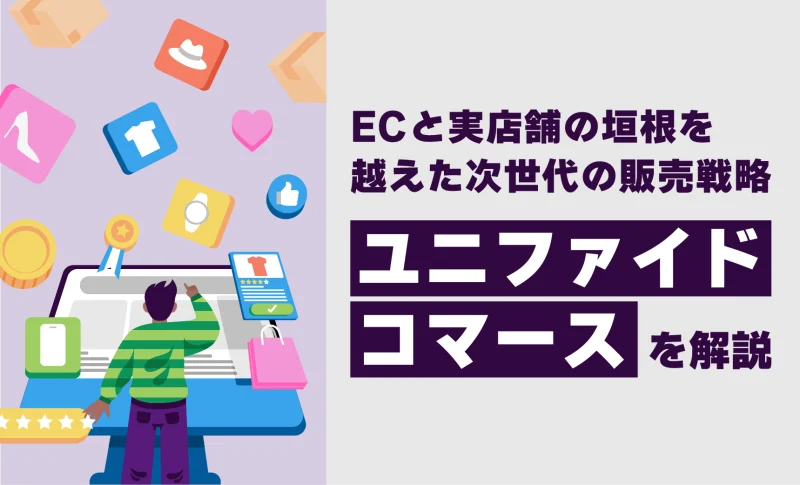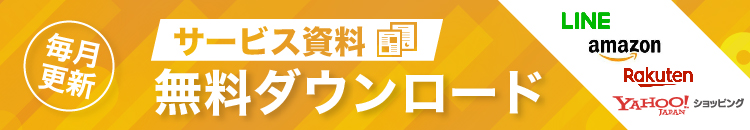ECや小売業界で注目されるユニファイドコマースは、オムニチャネルの進化系とされるマーケティング概念です。
オンラインとオフラインの統合をさらに強化し、シームレスな購買体験を提供することを目的としています。
今後、小売業における重要性が高まると予想されます。
今回はユニファイドコマースの意味や具体的な施策、EC事業者が取り組むメリットについて解説します。
目次
ユニファイドコマースとは
ユニファイドコマース(Unified Commerce)とは、「統合された商取引」を意味し、実店舗やECサイト、コールセンターなどのチャネル間の隔たりをなくし、統一された購買体験を提供するマーケティング手法です。
ユニファイドコマースの施策としては、以下のようなサービスが挙げられます。
購買データを活用したEC誘導
実店舗で化粧品のトライアルセットを購入した会員に対し、使用期間を考慮した本製品のキャンペーンメルマガやプッシュ通知を送り、ECサイトへ誘導します。
購入後のフォロー
実店舗で革靴を購入した顧客に、その日の夜にサンクスメールを送信し、「革のメンテナンス方法」や「靴に合うコーディネート」などの情報を提供します。また、ECサイトで購入できるメンテナンスグッズも紹介します。
店舗スタッフの接客
実店舗やECサイトの購入履歴、コールセンターの問い合わせ履歴を統合した顧客データベースを活用し、店舗スタッフやカスタマーサポートが最適な接客を提供できるようにします。
ユニファイドコマースが重要視される理由
近年、実店舗とECサイトの両方で商品を販売する企業が増えています。しかし、チャネル間のデータが連携していないと、顧客体験を向上させることは難しくなります。
たとえば、ECサイトのレコメンドエンジンが実店舗の購入履歴と連携していない場合、すでに購入済みの商品が何度もレコメンドされる可能性があります。
単なる検索キーワードや属性によるレコメンドでは、顧客が求める情報を適切なタイミングで提供することができません。
この課題を解決するため、チャネルを統合し、より最適な購買体験を提供するユニファイドコマースが注目されています。
オムニチャネルの進化系としてのユニファイドコマース
ユニファイドコマースは、オムニチャネルを進化させたマーケティング手法といえます。
オムニチャネルは、実店舗やECサイト、チラシ、SNS、DMなど、あらゆるチャネルで顧客が希望する商品を同じように購入できる環境を作ることを目的としています。
一方、ユニファイドコマースは、オムニチャネルの枠を超え、会員属性や購買履歴、コールセンターへの問い合わせ履歴、アプリの利用状況、SNSの行動、ブランドサイトの閲覧履歴などのデータを統合し、顧客ごとに最適な商品やサービスを最適なタイミングで提供することを目指します。
つまり、ユニファイドコマースは「いつでもどこでも買えるオムニチャネル」にOne to Oneマーケティングの要素を加えた販売手法といえます。
ユニファイドコマースとOMOの違い
ユニファイドコマースと似たマーケティング用語にOMO(Online Merges with Offline)があります。
OMOは「オンラインとオフラインの融合」を意味し、たとえばSNSで商品を見つけ、実店舗で確認し、最終的にECサイトで購入するといったシームレスな購買行動を指します。
一方、ユニファイドコマースは、オンライン・オフラインを問わずチャネルの垣根を超えた購買体験の統合に重点を置いています。
両者の違いを明確に分けるのは難しいですが、OMOはチャネルの融合に、ユニファイドコマースは購買体験の統合に重きを置いている点が主な違いといえます。
ユニファイドコマースの効果
ユニファイドコマースによるOne to Oneマーケティングの実現
ユニファイドコマースでは、広告のような予測的なセグメントではなく、実際の購買データに基づいた施策を展開できます。ECサイトや店舗のPOSレジを通じて収集したデータを活用し、各顧客に最適なアプローチを実施することで流入率の向上が期待できます。
ただし、データを有効活用するためには、BIやCRMツールに統合し、施策へ反映させる環境整備が必要です。
データ統合とセグメント分けの効率化
ユニファイドコマースでは、ECやアプリ、店舗などから得たデータを統合し、細かくセグメント分けする作業が求められます。
そのため、BIやCRM導入時には、スムーズなデータ統合と詳細な顧客セグメント分けが可能なシステムを選ぶことが重要です。
- データ統合の対策例
- 店舗とECの会員データを連携
- ポイントプログラムをECと店舗で統一
- 在庫情報を一元管理
- 接客や問い合わせ履歴を顧客データに統合
- 分析結果の可視化とツール選定
分析結果を適切に理解し、マーケティングに活用するには、視覚的に分かりやすく表示できるシステムの導入が効果的です。
ただし、導入したツールが活用されなければコストの無駄になります。
ユニファイドコマースのメリット
顧客満足度・売上の向上
バックエンドシステムを統合し、統合されたデータを効果的に活用すれば、顧客満足度・売上の向上につながります。
例えば「過去の購入履歴に基づいて顧客の関心がありそうな商品をアプリでレコメンドし、ECサイトでの商品閲覧を促す」といったアプローチが可能です。
さらに、顧客が実際の商品を見て購入を検討したい場合「在庫のある店舗を案内して来店を促す」「店舗でアプリを提示してもらい、ECサイトで貯めたポイントを使用する」「ECサイトで登録したクレジットカードでの決済を店舗でも可能にする」といった購買体験を提供できます。
質の高い顧客体験が提供できれば、売上の向上やリピート購入を促すことが可能となります。
業務コストの削減
顧客管理や在庫管理、物流管理、決済・入金管理など、各業務やチャネルで異なるシステムを使用している場合「データを都度出力して連携するのに手間がかかる」「入力ミスや確認漏れによるトラブルが生じやすいという」といった問題が生じる可能性があります。
さらに使用するシステムの数が多い場合、システムの利用や保守・改修に関わるコストが増加し、ベンダーへの問い合わせの手間が増えるデメリットも生じます。
ユニファイドコマースを導入し、各業務やチャネルで使用するシステムを統合すれば「業務の効率化」や「管理コストの削減」が期待できるでしょう。
経営判断が行いやすくなる
データが統合されると、ECサイトや実店舗などの個別チャネルの顧客データではなく「顧客のチャネルを超えた行動データ」が一元的に把握できます。
行動データが把握できるため「会社全体の売上を最大化する戦略の策定」や「最適な在庫管理」が実現可能です。
また「チャネルごとにデータを抽出する」「照合して分析する」といった手間がなくなるため、迅速な経営判断が行いやすくなります。
まとめ
ユニファイドコマースは、オムニチャネルの進化系であり、オンライン・オフラインの統合を強化し、シームレスな購買体験を提供する手法です。
購買データを活用したEC誘導や購入後のフォロー、店舗での接客の最適化など、チャネルを超えた統合が可能になります。
OMOと異なり、単なるチャネルの融合ではなく、購買体験の統合に重点を置いており、One to Oneマーケティングの実現が可能です。
実際の購買データを活用することで、適切な施策を実施し、顧客満足度向上や売上増加につながります。
また、業務システムの統合により、管理コスト削減や経営判断の迅速化も期待できます。
適切なデータ活用とシステム導入を行うことで、企業の競争力を高められるでしょう。
EC運営に役立つ資料が満載!

EC運営に役立つセミナーを毎月開催中!

当社のEC運営代行サービスについて