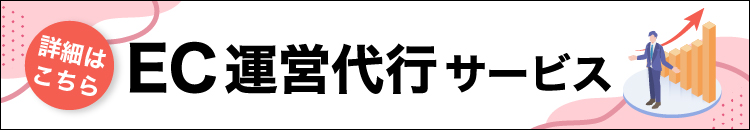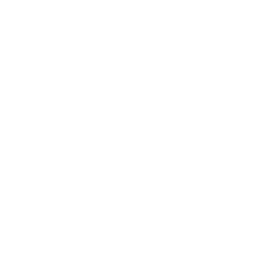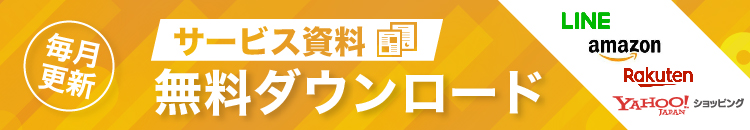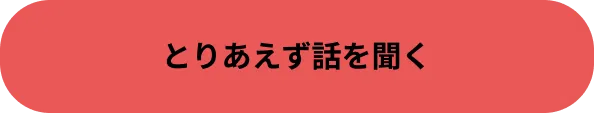ネットショップやECサイトで商品を配送する際は、配送業者に依頼します。
配送方法にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なるため、商品に適した配送方法を選ぶことが大切になります。
ネットショップやECサイトで利用される配送方法について、その特徴やメリット・デメリットを解説します。
配送方法の種類
ネットショップやECサイトでよく利用される配送方法は、宅急便とメール便(ポスト投函便)が主流です。今回は、それらに加えて軽貨物配送や国際宅急便(国際郵便)についても、それぞれの特徴を紹介します。
宅配便
ネットショップやECサイトで最も利用される配送方法の一つです。ヤマト運輸や佐川急便が提供する宅配サービスのほか、日本郵政の「ゆうパック」も宅配便に含まれます。
出荷から到着までが早く、紛失や破損時の補償があり、代金引換の利用も可能など、サービスが充実しています。
一方で、メール便(ポスト投函便)と比べると送料が高く、配送距離や重量、サイズによって費用が変動する点には注意が必要です。
補償が必要な高価格の商品や、大型商品、食品など、メール便で送れない商品の配送に適しています。
メリット
・輸送がスピーディーで、日時や時間指定が可能
・配送追跡や紛失・破損時の補償があり、安心感が高い
・冷凍・冷蔵商品の配送にも対応
デメリット
・メール便(ポスト投函便)と比べると送料が高い
・配送距離や重量、サイズによって費用が変動する場合がある
・対面受け取りが必要な場合、不在時に受け取れない
細かなサービス内容は配送業者や荷物のサイズによって変わります。
詳しくは各配送サービスをご確認ください。
メール便(ポスト投函便)
メール便(ポスト投函便)は、郵便受けやポストに直接配送される宅配サービスです。対面受け取りが不要なため、配送時間を気にせず受け取れる点がお客様にとって大きなメリットとなります。
配送料は全国一律で変動が少なく、低コストでの発送が可能です。
宅配業者やサービスによっては配送追跡や補償が付く場合もありますが、宅配便と比べると補償額が低いことが多く、補償がない場合は紛失リスクに注意が必要です。
配送速度は宅急便と同等か、それよりも遅くなることがあり、郵便受けに入らない場合は対面受け取りになることもあります。安価で小型の商品を送る際に適した配送方法です。
メリット
・配送料が安く、コストを抑えられる
・梱包の手間が少なく、発送が簡単
・受け取りが容易で、お客様の負担が少ない
デメリット
・配送可能な荷物のサイズに制限がある
・配送日時指定や代金引換が利用できない
・補償額が低く、補償がない場合は紛失リスクがある
・冷凍・冷蔵商品の配送には対応していない
温度管理が不要なサプリメントなどは送れますが、冷凍・冷蔵が必要な食品には適さないため、商品によって向き不向きがある配送方法です。
軽貨物配送
軽貨物配送は、軽貨物トラックを利用した配送サービスです。大手企業から中小企業、個人事業者まで幅広く配送業務を担っています。
宅急便のサイズを超える商品は、軽貨物配送を利用することがあります。
特に、大型の電化製品や家具を扱うネットショップ・ECサイトでは、軽貨物配送と契約することでコスト削減につながる場合があります。
また、ペット輸送や貸し切り配送など、特殊なサービスを提供する業者もあり、柔軟な対応が可能です。
近年、小口貨物を扱う軽貨物配送業者が増え、必ずしも大型荷物専用ではなくなっています。
しかし、業者ごとに得意な配送形態が異なり、ルート配送に特化した業者や全国対応が難しい業者などが存在するため、事前の検討が必要です。配送時間やコスト、集荷のタイミングなどを確認し、自社の商材や販売形態に適した業者を選ぶことが重要となります。
メリット
・大型商品や特殊配送に対応可能
・契約次第で宅急便より低コストで利用できる
・ルート配送や貸し切り配送など、商材に応じた選択が可能
デメリット
・配送時間やコスト、集荷タイミングは業者ごとに異なるため確認が必要
・コンビニ受け取りや代金引換が利用できない場合がある
・商材と配送業者の特性が合わないと、かえってコストがかかることがある
宅急便やメール便と組み合わせて活用することで、取り扱い商品の幅を広げたり、配送の選択肢を増やしたりすることができ、柔軟な配送体制の構築につながります。
国際宅急便(国際郵便)
国際宅急便(国際郵便)は、海外へ商品を発送する際の配送方法です。
ヤマト運輸や佐川急便のほか、DHLやFedExなど国際配送を専門とする業者が知られています。
日本郵政が扱う場合は「国際郵便」、民間企業が配送する場合は「国際宅急便」と呼ばれます。
配送方法には船便や航空便があり、商品特性に応じたプランを選択することでコストを抑えることが可能です。
小口・大口配送、特殊配送、定期発送など柔軟な対応もできるため、配送業者と相談し、適切なプランを決めましょう。
国内配送と異なり、到着までに時間がかかるため、事前にお客様へ配送予定を伝えておくことが重要です。
商品の価格に対して送料が高額になると、購入キャンセルにつながる可能性があるため、注意が必要です。
また、大型荷物(重量20kg超など)は配送できない場合があるため、事前に業者へ確認しましょう。
メリット
・通関手続きを配送業者が代行し、手間を軽減できる
・配送点数やサイズ、商品特性に応じた柔軟なプラン設計が可能
・最短翌日到着など、スピーディな配送が可能(条件により異なる)
デメリット
・配送に時間がかかる場合がある / 費用が高額になる可能性がある
・燃料サーチャージの影響で料金が変動することがある
・大型荷物の発送が制限される場合がある
燃料サーチャージは、燃料費の高騰により追加される料金です。近年の燃料費高騰の影響もあり、配送業者への事前確認をおすすめします。
食品や温度管理が必要な商品を発送する場合
食品を発送する際、温度管理が必要な場合があります。
その場合は冷蔵便(チルド便)・冷凍便(クール便)といった宅急便で配送を行う必要がありますが、どちらがどういう配送方法なのか、自社の商品はどちらで送ればいいのかなどを、配送の特徴から考えてみましょう。
冷蔵便(チルド便)
冷蔵便は、約0℃~10℃の温度帯で管理しながら配送を行うサービスです(具体的な温度帯は配送業者によって異なります)。
荷物を低温で保つことで品質維持ができ、生鮮食品や医薬品・化粧品など温度管理が求められる商品の配送に適しています。宅配便と同様に、配送追跡・紛失・破損補償・代金引換が利用できます。
ただし、通常の宅配便より料金が高く、発送前の予冷や保冷剤の準備など、ショップ側での管理が必要です。
また、サイズや重量に制限があるため、大量注文の場合は複数口での発送になることもあります。
メリット
・生鮮食品や医薬品などの品質を維持できる
・配送追跡・補償・代金引換が可能
・商品を凍らせずに低温で管理できる
デメリット
・通常の宅配便より料金が高い
・発送前の予冷や保冷剤の管理が必要
・サイズや重量に制限があり、大型荷物には向かない
冷凍便(クール便)
冷凍便は、約-10℃~-15℃で温度管理を行い、荷物を凍結状態のまま配送するサービスです(具体的な温度帯は配送業者によって異なります)。
冷凍食品や魚介類など、解凍させたくない商品の配送に適しており、発泡スチロールやドライアイスを利用した梱包の工夫で、さらに低温での輸送も可能です。
ただし、冷蔵便と同様に発送前の予冷や梱包管理が必要で、温度を保つだけで荷物自体を冷却するわけではないため、ショップ側での温度管理が重要です。
配送業者によっては「冷凍便」と「クール便」の温度帯が異なることもあるため、事前に確認しましょう。
メリット
・冷凍状態を維持できるため、溶かさずに配送可能
・配送追跡・補償・代金引換が利用できる
・梱包の工夫で、より低温管理も可能
デメリット
・通常の宅配便より料金が高い
・発送前の予冷や保冷剤の準備が必須
・サイズや重量の制限があり、大型荷物の配送は難しい
まとめ
ネットショップ・ECサイトの配送方法には、宅急便、メール便、軽貨物配送、国際宅急便などがあり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。自社の商品に合った配送方法をしっかり見定めて、効率良い配送方法を選ぶようにしましょう。
EC運営に役立つ資料が満載!

EC運営に役立つセミナーを毎月開催中!

当社のEC運営代行サービスについて