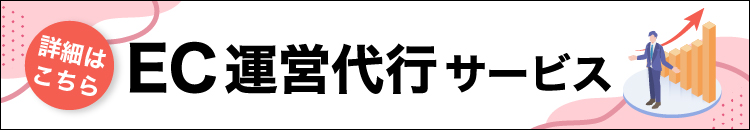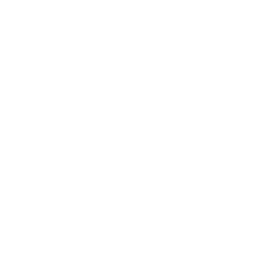-
-
- 2025年8月29日から9月5日までのECに関連する注目のニュースを5つピックアップして紹介します。本ニュースは物販ビジネス専門メディア「コマースピック」の提供です。
本日ご紹介するニュースは次の5つです。
1、調査により通販事業者のAI導入率が12.7%と発覚
2、Yahoo!ショッピングが認定制度で食品選びを支援
3、auコマース&ライフがLINE連携を強化し再購入を促進
4、DGBTが紹介サービスで新規顧客獲得を支援
5、ソーシャルギフトが企業利用で新潮流に1.調査により通販事業者のAI導入率が12.7%と発覚
ECシステム構築を手掛けるエルテックスは2025年9月1日、25回目となる「通信販売事業関与者の実態調査2025」を公表しました。全国の通販事業者300名を対象とした調査で、AI導入率は12.7%と、2023年比で4.0ポイント増加したことが明らかになりました。「導入済み」と「導入予定」を合わせた割合は32.7%で変化はないものの、「検討・情報収集中」は+8.5ポイントと大幅に増え、関心の高まりが浮き彫りとなりました。AI活用領域の関心はフロントエンドに集中。複数回答では「ECストアのサイト内検索」が最多で、「チャットボット・接客ツール」「マーケティング分析」が続きました。単一回答でも検索がトップ、次いでチャットボット、リコメンドエンジンが選ばれており、消費者接点に直結する機能への期待が高い結果です。一方で「コールセンター支援」などは関心が低下しました。2.Yahoo!ショッピングが認定制度で食品選びを支援
LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」は2025年9月2日、食品カテゴリ強化に向けて「認定グルメ」制度を開始しました。審査員による試食評価やユーザーレビューを基に、「至高グルメ」「特選グルメ」「評判グルメ」の3種類のアイコンを付与し、信頼性の高い商品選びを支援します。第1回審査では料理研究家リュウジ氏らが14商品を実食し、「骨取りトロサバ」や「天空のチーズケーキ」が高評価を得ました。従来、食品カテゴリは人気が高い一方で「商品が多すぎて選べない」との声も多く、Yahoo!ショッピングにグルメのイメージが薄い点も課題でした。新制度はこうした不安を解消し、「グルメといえばYahoo!ショッピング」という想起強化を狙っています。認定制度は「信頼できる基準」と「実際のレビュー」の両面を活用する仕組みであり、消費者には選びやすさを、出店者には訴求力をもたらす施策として注目されます。3.auコマース&ライフがLINE連携を強化し再購入を促進
auコマース&ライフは総合EC「au PAY マーケット」で、出店店舗向けに「LINE通知メッセージ」と「LINE配信パーソナライズ化ツール」を2025年9月1日に提供開始しました。課題だった「重要なお知らせがメールBOXで埋もれる」「能動的な友だち登録の獲得が難しい」「一人ひとりに適した配信を行いたい」に対応します。前者は、友だち登録の有無にかかわらず購入者の電話番号を基に注文・発送通知をLINEで配信でき、自然な流れで友だち登録の増加を狙える設計です。後者は、au PAY マーケットの購買データと連携し、精度の高いメッセージ配信を実現。ファン化や再購入の促進に資するとしています。4.DGBTが紹介サービスで新規顧客獲得を支援
デジタルガレージ系のDGビジネステクノロジーは2025年9月3日、EC事業者向けのリファラルマーケティングサービス「NaviPlusフレンズ」を提供開始しました。既存顧客の紹介を活用することで、広告費に依存せず費用対効果の高い新規顧客獲得を実現する仕組みです。利用企業の中には開始1週間で85件の新規会員を獲得した事例も報告されており、早期から成果を発揮しています。導入はWebサイトにタグを設置するだけで可能。専用管理画面で特典設定や効果測定を一元管理でき、成果連携も自動化されているため担当者の負担を軽減します。会員登録を起点とする設計により、紹介者・被紹介者双方が参加しやすく、初回購入への転換を自然に促せる点も特長です。5.ソーシャルギフトが企業利用で新潮流に
ギフトモール オンラインギフト総研は、ソーシャルギフト利用経験者2,250名を対象に実施した調査結果を発表しました。利用者の43.7%が企業からのギフトを受け取った経験があり、そのうち95.6%が「継続して受け取りたい」と回答。個人間の贈答ツールの枠を超え、販売促進や景品、成約記念品などビジネスシーンへの浸透が進んでいます。受け取り経験がない人でも80.3%が「貰ってみたい」と答えており、潜在需要の高さも明らかになりました。企業の活用目的は「販売促進・キャンペーン」が55.4%で最多、次いで「景品」26.7%、「成約記念品」13.3%。「お中元・お歳暮」といった高単価ギフトでも一定の利用が進み、従業員への感謝や帰属意識向上に使うケースも11.0%確認されています。メリットは即時配布や在庫管理不要、効果測定が容易な点。小川所長は「企業のBtoC関係強化の有力手法として普及が加速する」と分析します。今後は高価格帯や顧客セグメント別の活用拡大が予測され、デジタル時代の新たな企業コミュニケーション手段として注目度を高めています。以上、ECの未来®NEWSでした。
-
EC運営に役立つ資料が満載!

EC運営に役立つセミナーを毎月開催中!

当社のEC運営代行サービスについて